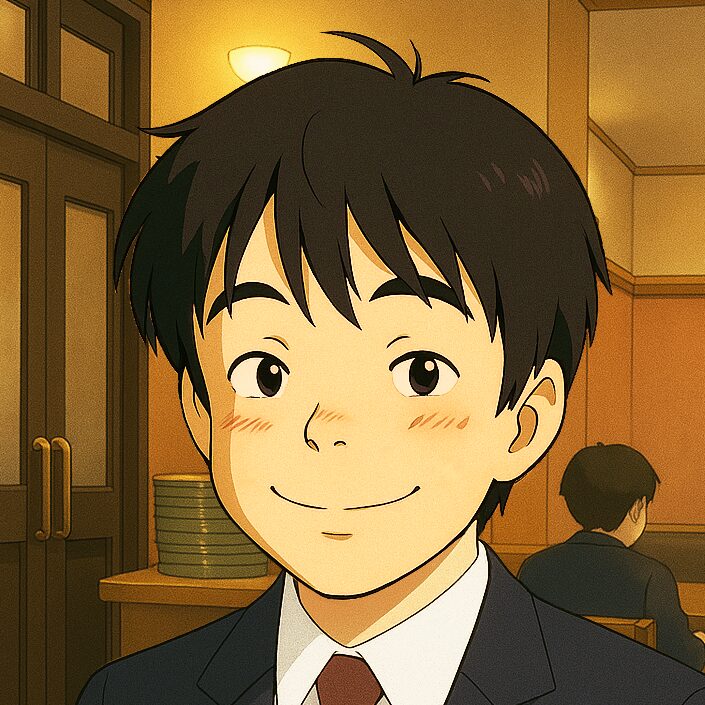高槻市の相続手続き、何から始めればいい?不動産オーナー様のための「最初のステップ」ガイド

相続が起きた時、こんな戸惑いはありませんか?(高槻市にお住まいの方へ)
- 「突然のことで、何から手をつければいいのか全く分からない…」
- 「高槻市内の土地や賃貸アパートなど、不動産の相続手続きはどうすれば?」
- 「手続きがたくさんありそうで、期限とかも心配…」
- 「相続人は自分たちだけだけど、具体的に何をどう進めればいいのだろう?」
- 「専門家に頼みたいけど、大げさにしたくないし、高槻市でどこに相談すればいいか…」
大切なご家族が亡くなられた悲しみの中で、すぐに様々な手続きを始めなければならないのが「相続」です。特に、交通の便も良く住みやすい高槻市のような場所に土地やご自宅、賃貸物件などの不動産をお持ちだった場合、その手続きは多岐にわたり、多くの方にとって初めての経験となるでしょう。「うちには関係ないと思っていたけれど…」と戸惑われる方も少なくありません。
この記事では、そんな相続の第一歩を踏み出す皆様へ、まず「何を知っておくべきか」「何をすべきか」を、大まかな流れに沿ってご紹介します。
まずは落ち着いて確認・行動を:相続発生直後の「やること」
相続は、故人が亡くなられた直後から始まります。慌ただしい時期ですが、まず最低限行うべきことがあります。
- 死亡診断書(死体検案書)の受け取り
今後の手続きの基本となる書類です。病院や警察から必ず受け取り、コピーを数部取っておきましょう。 - 死亡届の提出(7日以内)
高槻市役所へ提出します。これが受理されないと火葬許可証が出ません。葬儀社が代行してくれる場合もあります。 - 火葬許可証の取得・葬儀の準備
葬儀社と打ち合わせを進めます。
この時期は精神的にも大変ですが、これらの手続きは期限も短いため、一つずつ確実に進めることが大切です。
少し落ち着いたら:相続の全体像を把握するための情報収集
葬儀などが一段落したら、本格的な相続手続きに向けて情報収集を始めます。
遺言書の有無を確認
故人が遺言書を残しているかで、手続きの進め方が大きく変わります。自宅、貸金庫、大阪法務局北大阪支局(自筆証書遺言保管制度)、高槻公証役場(公正証書遺言)などを確認しましょう。自筆の遺言書を見つけたら、すぐに開封しないでください。家庭裁判所の「検認」が必要な場合があります。
相続人を確定する
誰が相続人になるのかを、故人の出生から死亡までの戸籍謄本等で正確に確定させます。配偶者は常に相続人ですが、お子様、ご両親、ご兄弟姉妹など、誰が該当するかを確認します。
財産と負債の調査
高槻市内の不動産(自宅、賃貸物件など)、預貯金、有価証券などのプラスの財産だけでなく、ローンなどのマイナスの財産も全てリストアップ(財産目録作成)します。高槻市役所で取得できる固定資産評価証明書や固定資産税納税通知書、登記事項証明書、金融機関への照会などが役立ちます。
相続方法を決める(原則3ヶ月以内)
財産と負債の全体像が見えたら、全て相続する「単純承認」、全て放棄する「相続放棄」、財産の範囲内で負債を弁済する「限定承認」のいずれかを選びます。「相続放棄」「限定承認」は家庭裁判所での手続きが必要です。
準確定申告(必要な場合・4ヶ月以内)
故人に所得があった場合、代わりに所得税の申告を行います。
この段階での情報収集と判断が、後の手続きをスムーズに進めるための基礎となります。特に戸籍収集や財産調査は時間と手間がかかることも多く、不動産の評価も関わってくるため、早めに全体像を掴むことが重要です。
財産の分け方と名義変更:高槻市の不動産相続の重要ポイント
相続人が複数いる場合、遺言書がなければ、誰がどの財産を相続するかを相続人全員で話し合う「遺産分割協議」が必要です。
遺産分割協議
相続人全員で合意を目指します。高槻市中心部の不動産は価値も高く、分割が難しい場合が多い(そのまま分ける、誰かが取得し代償金を払う、売却して分ける、共有するなど)ため、評価方法も含めて慎重な話し合いが必要です。賃貸物件の場合は、家賃収入や管理の引き継ぎも話し合います。
遺産分割協議書の作成
全員が合意したら、その内容を書面にします。不動産については、登記簿通りに正確に記載し、相続人全員が署名・実印を押印します。これは後の不動産名義変更(相続登記)に必須です。
不動産の名義変更(相続登記)
相続した不動産の名義を故人から相続人へ変更します。2024年4月から義務化され、相続を知った日から3年以内の申請が必要です。大阪法務局北大阪支局へ申請しますが、必要書類が多く手続きも複雑なため、司法書士に依頼するのが一般的です。
相続税の確認(必要な場合):申告・納付は10ヶ月以内
相続財産の総額が基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。
相続財産の評価
特に高槻市中心部の不動産は評価額が高くなりやすく、路線価など専門的な評価方法が用いられます。評価額によって税額が大きく変わるため、正確な評価が重要です。
申告と納付
相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に、茨木税務署(高槻市の管轄)へ申告・納付します。
相続税の計算や申告は非常に複雑なため、税理士、特に相続に詳しい税理士への相談が不可欠です。
高槻市での不安な手続き、「丸ごと任せたい」もお手伝いできます
ここまで大まかな流れを見てきましたが、実際にはもっと細かい手続きや、個々のケースに応じた対応が必要になります。「自分たちだけで進めるのは不安だ」「手続きが多くて大変そう」「信頼できる専門家にまとめてお願いしたい」と感じられる方も多いのではないでしょうか。
私たち行政書士は、相続手続きの最初の入口として、皆様のお話をじっくり伺い、
- 何から始めればよいか、全体の手続きの流れのご案内
- 相続人調査(戸籍収集)のお手伝い
- 遺産分割協議書の作成サポート
- その他、高槻市役所への各種届出書類の作成
など、相続に関する様々なお手続きをサポートさせていただきます。
また、不動産登記が必要な場合は信頼できる司法書士を、相続税の申告が必要な場合は税理士を、もし相続人間で争いが生じてしまった場合は弁護士を、といったように、高槻市対応の他の専門家と連携し、お客様の状況に合わせてサポートすることも可能です。
初回のご相談は無料です。まずはお客様の状況やお悩みをお聞かせください。秘密厳守で対応いたします。
相続という大変な時期を、少しでも安心して乗り越えていただけるよう、私たちが専門家としてしっかりとサポートさせていただきます。どうぞお気軽にご連絡ください。