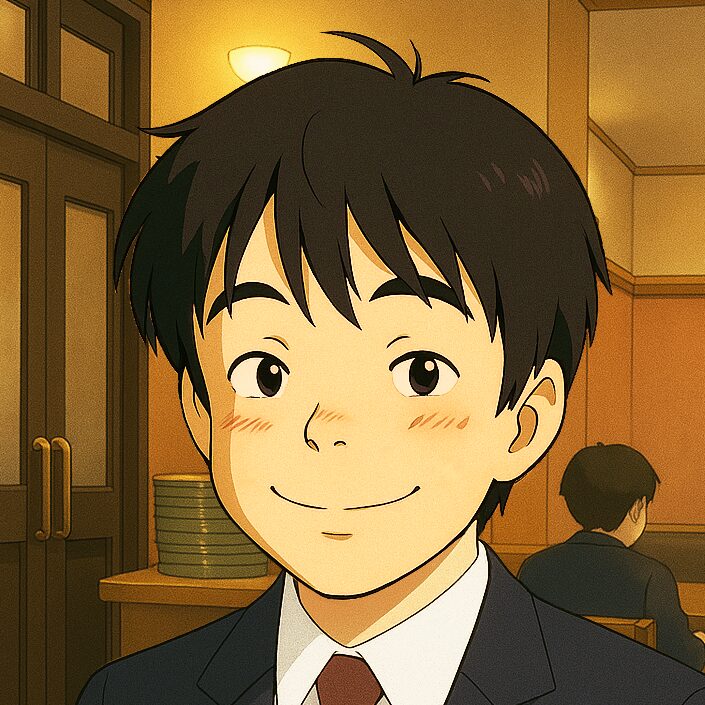豊中市で相続人に認知症の方がいたら…? 知っておきたい相続手続きと「転ばぬ先の杖」

こんな心配事、ありませんか?(豊中市にお住まいの方へ)
- 「親が高齢になり、最近少し物忘れが増えてきた。もし認知症になったら、豊中市の実家の相続はどうなるのだろう?」
- 「相続人の一人に、認知症の疑いがある。遺産分割の話し合いはできるのだろうか?」
- 「将来、自分が認知症になったら、大切にしてきた千里中央のマンションやアパートの管理はどうなってしまうのか?」
- 「相続手続きが止まって、不動産の売却や活用ができなくなるのは困る…」
- 「家族が揉めないように、元気なうちに何か準備しておきたいけれど、何から始めればいいか分からない」
大切なご家族の健康は何よりですが、近年、認知症は誰にとっても身近な問題となっています。もし、ご自身やご家族(相続人となる方)が認知症になった場合、相続の手続きが通常通りに進められなくなる可能性があることをご存知でしょうか?
特に、豊中市のように不動産価値が高い地域で土地や建物、賃貸アパートなどを所有されている場合、手続きがストップしてしまうと、管理や処分に大きな支障が出てしまうことも考えられます。
「相続人の中に認知症の方がいる」と、何が問題になるの?
相続が発生した場合、通常は相続人全員で「誰がどの財産を、どのように引き継ぐか」を話し合って決める「遺産分割協議」を行います。しかし、相続人の一人に認知症などによって判断能力が不十分な方がいると、次のような問題が起こります。
- 遺産分割協議ができない
遺産分割協議は、内容を理解し、自分の意思で合意する能力(意思能力)が必要です。認知症でこの能力が低下していると判断されると、本人は協議に参加できません。 - 勝手に進めた協議は無効に
判断能力のない相続人を除外したり、無理に参加させたりして行った遺産分割協議は、法的に無効となる可能性が高いです。 - 不動産の売却や預貯金の解約がストップ
遺産分割協議が成立しないと、豊中市内にある故人名義の不動産を売却したり、銀行口座を解約したりできません。大切な資産が「凍結」された状態になってしまいます。 - 借金があっても「相続放棄」ができない
相続放棄も本人の意思表示が必要なため、判断能力がなければ手続きできません。
このように、豊中市にお住まいのご家族でも、相続手続き全体がストップし、長期間にわたって問題が解決しないケースも少なくありません。
相続が発生してしまったら…「成年後見制度」という選択肢
もし、相続が発生した時点で相続人に認知症の方がいる場合、「成年後見制度」を利用して手続きを進める方法があります。これは、家庭裁判所(豊中市の場合は大阪家庭裁判所)が、判断能力の不十分な方の代わりに財産管理や契約などを行う「成年後見人」を選任する制度です。
成年後見人が、ご本人に代わって遺産分割協議に参加することで、法的に有効な形で相続手続きを進めることができます。
ただし、この制度を利用するには、家庭裁判所への申し立てが必要で、選任までに数ヶ月かかることもあり、費用も発生します。また、一度選任されると、原則としてご本人が亡くなるまで後見は続き、財産管理について家庭裁判所への報告義務が生じるなど、ご家族にとって負担となる側面もあります。
最も有効なのは、元気なうちの「事前の備え」
成年後見制度は有効な手段ですが、できれば避けたい、あるいはもっとスムーズに進めたい、と考える方も多いでしょう。そこで重要になるのが、判断能力がしっかりしているうちに、将来に備えて対策を講じておくことです。
特に有効な対策として、以下の2つが挙げられます。
1.「遺言書」を作成しておく
ご自身の財産を「誰に」「何を」「どのように」遺すかを明確に記した遺言書があれば、原則として相続人全員での遺産分割協議は不要になります。
なぜ有効か?
相続人の中に判断能力が不十分な方がいても、遺言書の内容に従って手続きが進められるため、成年後見制度を利用せずに済む可能性が高まります。
ポイント
- 必ず判断能力があるうちに作成する。
- 形式不備で無効にならないよう、公正証書遺言(公証役場で作成する遺言)が安心です。豊中市内には公証役場がないため、梅田・本町など近隣の公証役場を利用することになります。
- 遺言の内容を実現する「遺言執行者」を指定しておくと、手続きがよりスムーズです。
2.「家族信託」を活用する
ご自身の財産(豊中市内の不動産、預貯金など)の管理や処分を、信頼できるご家族(受託者)に託す契約を生前に結んでおく方法です。
なぜ有効か?
もしご自身が認知症になっても、契約に基づき受託者が財産の管理(家賃収入の受け取り、修繕の手配、不動産の売却など)を継続できるため、資産凍結を防ぐことができます。
ポイント
- 遺言書ではできない、ご自身が亡くなった後の次の世代への資産承継まで、柔軟に設計できる場合があります。
- 元気なうちにご家族と話し合い、信頼できる人に託すことが重要です。
どちらの方法が適しているかは、ご家族構成や資産状況、ご自身の想いによって異なります。
豊中市での相続・認知症対策なら、私たち行政書士へ
「遺言書を作りたいけど、どう書けばいいか分からない」
「家族信託に興味があるけど、うちの場合はどうだろう?」
「将来のために、何から準備すればいいか相談したい」
そのような時は、ぜひ私たち行政書士にご相談ください。相続や遺言、成年後見、家族信託に関する専門知識をもとに、豊中市のお客様一人ひとりの状況に合わせた最適な備えをご提案いたします。
私たち行政書士ができること(豊中市対応)
- お悩みやご希望のヒアリング
まずはお客様のお話をじっくり伺います。 - 最適な生前対策のご提案
遺言書、家族信託など、メリット・デメリットをご説明し、選択のお手伝いをします。 - 遺言書作成のサポート
法的に有効で、お客様の想いを反映した遺言書(自筆証書・公正証書)の作成を支援します。 - 家族信託契約書の作成サポート
ご意向に沿った信託契約の設計・作成をお手伝いします。 - 成年後見制度の利用サポート
必要な場合の申し立て手続きを支援します。 - 相続発生後の手続きサポート
遺産分割協議書の作成や各種名義変更など、相続に関する手続きを代行します。 - 「丸ごと任せたい」ニーズへの対応
司法書士、税理士、弁護士など、豊中市対応の他の専門家とも連携し、ワンストップでサポートいたします。
初回のご相談は無料です。秘密厳守で対応いたしますので、安心してご相談ください。
元気な今だからこそできる備えがあります。大切な資産とご家族の未来を守るために、私たちと一緒に「転ばぬ先の杖」を用意しませんか?