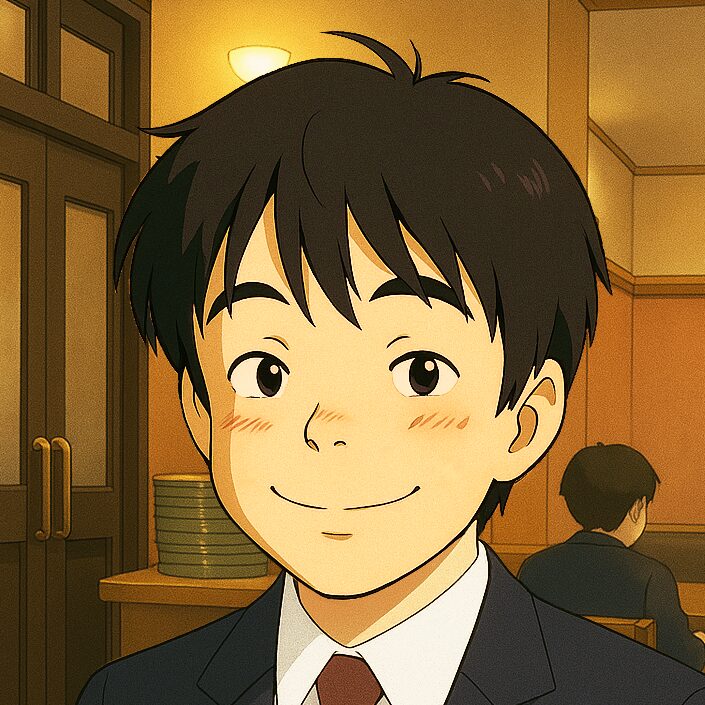高槻市で金融資産が多い方の生前対策|相続税で損しない遺言書・相続準備のポイント

大阪と京都の間に位置し、暮らしやすいベッドタウンとして発展してきた高槻市。この高槻市で、ご自身の資産形成を着実に進めてこられた投資家の皆様。大切に築き上げてきたその金融資産を、将来どのようにご家族へ引き継いでいくか、お考えになったことはありますでしょうか?
「自分はまだ元気だから大丈夫」「家族仲が良いから揉めるはずがない」とお考えかもしれません。しかし、金融資産が多い場合の相続は、手続きが煩雑になるだけでなく、相続税の負担が大きくなったり、分割方法を巡って思わぬトラブル(いわゆる「争族」)に発展したりするケースも、ここ高槻市でも決して少なくありません。
ご自身の意思を反映し、ご家族が円満に資産を引き継げるようにするためには、元気なうちから「生前対策」を始めることが極めて重要です。このコラムでは、高槻市およびその近隣で金融資産を多くお持ちの方が今すぐ始めるべき相続準備について、遺言書と相続税のポイントを中心にご紹介します。
1. なぜ金融資産が多い方に相続対策が必要なのか?
相続対策が必要な理由は、主に以下の3点です。
- 金融資産特有の相続手続きの煩雑さ
株式、投資信託、外貨建て資産、ネット証券など、資産の種類や保有する金融機関が多岐にわたる場合、相続発生後の財産調査や名義変更手続きは非常に複雑になります。 - 相続税負担の可能性
アッパーマス層の場合、相続財産の総額が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える可能性が高くなります。適切な対策を講じなければ、多額の相続税が課され、納税資金の確保に苦労することも考えられます。 - 「争族」の回避
金融資産は価値が明確な一方で、株式のように分割しにくいものや、評価額を巡って意見が分かれやすいものもあります。「誰がどの銘柄を相続するか」で揉めてしまい、家族関係が悪化するケースを防ぐ必要があります。
これらのリスクを回避し、ご自身の築いた資産と家族への想いをスムーズに次世代へ繋ぐために、生前対策は不可欠なのです。
2. 現状把握:まずは自分の資産をリストアップ
相続対策の第一歩は、ご自身の資産状況を正確に把握することです。
- 金融資産の棚卸し
- 預貯金(銀行名、支店名、口座番号、おおよその残高)
- 上場株式・投資信託(証券会社名、銘柄、数量、取得価額、現在の評価額)
- 非上場株式(会社名、保有株数)
- 債券(国債、社債など)
- 生命保険(保険会社名、受取人、死亡保険金額)
- 外貨建て資産(種類、保管場所、評価額)
- その他(金、プラチナなど)
- 不動産
高槻市内にあるご自宅やマンション、駐車場はもちろん、市外に所有する不動産もリストアップしましょう。(所在地、面積、固定資産税評価額など) - 負債
住宅ローン、借入金など
これらの情報を一覧表(財産目録)にまとめておくと、現状分析や具体的な対策を検討する上で非常に役立ちます。エンディングノートなどを活用するのも良いでしょう。
3. 争族対策の要:遺言書の作成
ご自身の意思で財産の分け方を指定できる「遺言書」は、金融資産が多い場合の相続対策において最も重要なツールの一つです。
- 遺言書のメリット
- 特定の相続人に特定の金融資産(例:「長男にA証券の〇〇株」など)を指定できる。
- 法定相続分とは異なる割合で財産を分けられる。
- 相続人以外の人(お世話になった人や団体など)にも財産を遺贈できる。
- 遺産分割協議が不要または簡略化でき、相続手続きがスムーズに進む。
- 遺言書の種類
- 自筆証書遺言
手軽に作成できるが、形式不備で無効になるリスクや、発見されない、改ざんされるリスクがある。法務局での保管制度を利用することも可能。 - 公正証書遺言
公証人が作成に関与するため、無効になるリスクが極めて低く、原本が公証役場に保管されるため安全確実です。金融資産が多い場合は、その記載方法も含め、公正証書遺言の作成を強くお勧めします。高槻市にお住まいの方であれば、高槻公証役場で作成が可能です。
- 自筆証書遺言
- 遺言執行者の指定
遺言の内容を実現する手続き(金融機関での名義変更など)を行う「遺言執行者」を指定しておくと、相続手続きがより円滑に進みます。信頼できる人や専門家(行政書士など)を指定することができます。
遺言書は、単に財産の分け方を決めるだけでなく、ご家族へのメッセージを添えることもできます。ご自身の想いをしっかりと形に残すためにも、高槻市の相続に詳しい専門家に相談しながら作成することをお勧めします。
行政書士による遺言書作成サポート(高槻市対応)
- ご意向のヒアリングと最適な遺言内容のご提案
- 自筆証書遺言の文案作成、形式チェック
- 公正証書遺言作成のための公証人との打ち合わせ、必要書類の収集、証人としての立ち会い
4. 相続税対策の基礎知識
金融資産が多い方にとって、相続税対策も重要な課題です。ここでは基本的な考え方をご紹介します。
(※ご注意:具体的な税務相談や税額計算、申告業務は税理士の独占業務です。ここでは一般的な制度紹介にとどめます。)
- 相続税の仕組み
相続税は、亡くなった方の財産総額から基礎控除額を差し引いた残りの額(課税遺産総額)に対して課税されます。税率は累進課税となっており、財産が多いほど税率が高くなります。 - 金融資産の評価
相続税計算上の金融資産の評価方法は、種類によって異なります。特に非上場株式などは評価が複雑になる場合があります。 - 生前贈与の活用
- 暦年贈与
年間110万円までの贈与であれば、原則として贈与税がかかりません。毎年コツコツと贈与することで、相続財産を減らす効果が期待できます。(※相続開始前一定期間内の贈与は相続財産に加算されるルール変更に注意が必要です。) - 相続時精算課税制度
原則60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上の子または孫に対し、累計2,500万円まで贈与税がかからず、相続時にその贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算する制度です。基礎控除(年110万円)も創設されました。
- 暦年贈与
- 生命保険の活用
死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。納税資金の準備や、特定の相続人に確実に現金を残す手段として有効です。 - 不動産活用等
不動産は現金よりも相続税評価額が低くなる傾向があるため、資産ポートフォリオの見直しも選択肢の一つです。(ただし、安易な組み換えはリスクも伴います。)
相続税対策は、ご自身の資産状況、家族構成、ライフプランなどを総合的に考慮して、長期的な視点で計画的に進める必要があります。必要に応じて、税理士などの専門家と連携して最適なプランを検討することが重要です。
5. 高槻市で相続相談なら、元気なうちに行政書士へ
「まだ先のこと」と考えがちな相続対策ですが、認知症などで判断能力が低下してからでは、遺言書の作成や生前贈与などの対策ができなくなってしまいます。元気で判断能力がしっかりしている「今」こそ、準備を始める最適なタイミングです。
私たち高槻市の行政書士は、「街の法律家」として、相続に関する様々なお悩みや手続きをサポートします。
- 相続全般を見据えた対策のご提案
遺言書作成だけでなく、財産管理や将来の認知症リスクに備える「任意後見契約」など、ご状況に合わせた生前対策を一緒に考えます。 - 必要な専門家との連携
相続税の具体的なシミュレーションや申告が必要な場合は税理士を、不動産登記が必要な場合は司法書士を、法的な紛争解決が必要な場合は弁護士を、といったように、必要に応じて信頼できる他の専門家と連携し、ワンストップでのサポートを目指します。 - ご家族への想いを形にするお手伝い
事務的な手続きだけでなく、皆様の「想い」を大切にし、円満な資産承継を実現するためのお手伝いをさせていただきます。
高槻市で金融資産を多くお持ちの皆様、ご自身の未来と大切なご家族のために、今すぐ相続準備を始めてみませんか? まずは、お気軽にご相談ください。